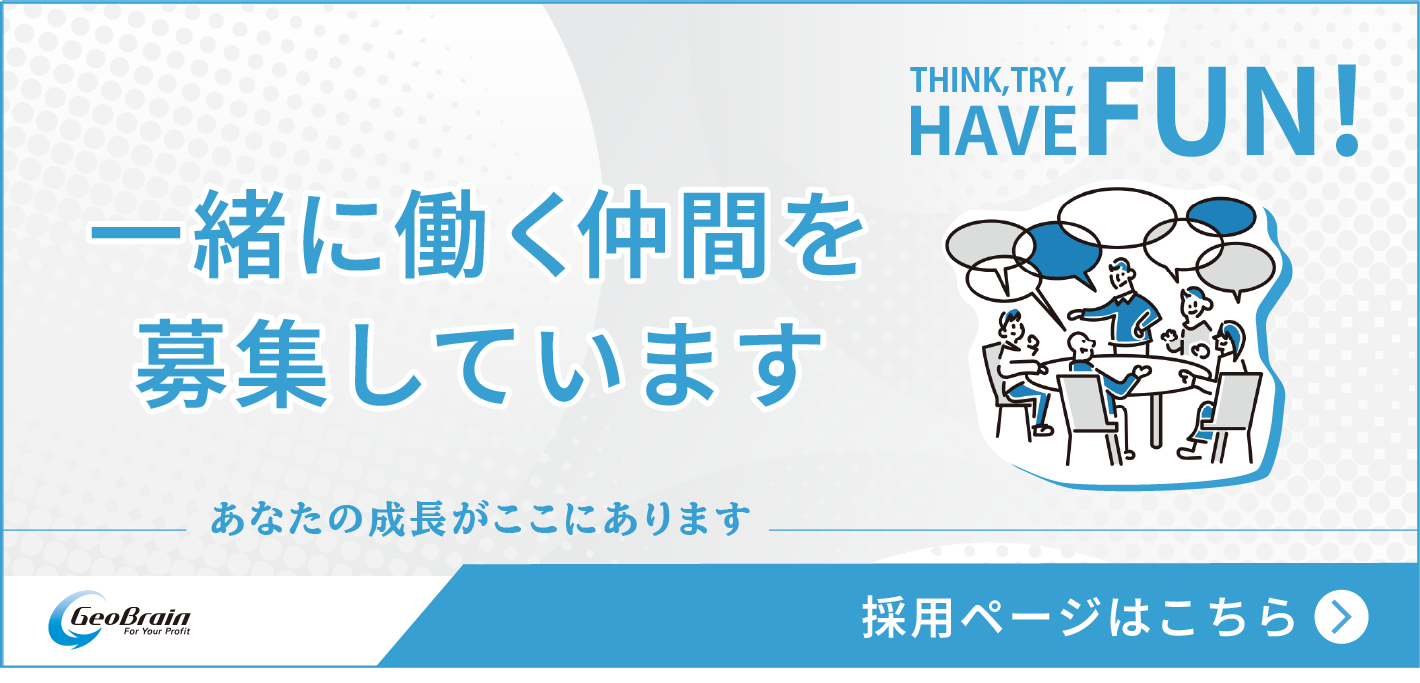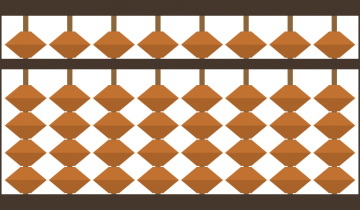「秋の雨が降れば猫の顔が三尺になる」ということわざがあります。
秋は晴れた日より雨の日の方が暖かいので、猫も顔を長くし喜ぶ という意味らしいです。
みなさん、こんにちは。
SS部八幡です。
突然ですが、問題です。
ーーーーーーーーーーーー
Aさんが天井の照明を交換しようとしています。
どのサイズの脚立を使用するのがいいでしょうか。
なお、Aさんの身長は160㎝、作業高さは「2.5m」とします。
①3尺 ②4尺 ③9尺
ーーーーーーーーーーーー
それでは解説という名の本題に移りましょう。
そもそも「尺」とは何でしょうか。※ChatGPTさんに簡単に教えてもらいました。
「尺(しゃく)」は、古代から使われている日本の長さの単位で、約30.3センチメートル(1尺 = 10寸)に相当します。日本では、尺を基準にした他の長さの単位(寸、分、厘など)が使用されてきました。 尺は、特に建築や工芸、着物の寸法など、さまざまな分野で使われてきました。また、尺を基にした「尺貫法(しゃっかんほう)」という日本独自の計測法が存在し、長さ、質量、容積などの単位が尺を中心に定められています。 現代では、メートル法が主流となっており、尺はあまり日常的に使われませんが、伝統的な技術や文化では今でも目にすることがあります。
「1尺=30.3㎝」
つまり、先程の問題の選択肢は
①3尺=90.9㎝、②4尺=121.2㎝、③9尺=272.7㎝ ということになります。
脚立の1段が約30㎝であることから、脚立の段数を数えれば「何尺」の脚立であるかが分かります。
この時、天板も1段として数えるため、3尺の脚立は天板を含めて3段ということになります。
「3尺(90.9㎝)+160㎝=250.9㎝になるから①でも正解じゃない?」
残念ながら違うんです。
理由は「脚立の天板に立っての作業は禁止」されているからです。

天板は踏み面も狭く、周りに支えるものもないためバランスを崩して転倒や転落する危険があります。
つまり、天板も含めて3段である3尺の脚立は、実際には2段目までしか使用できないので、
作業高さにちょっぴり届きません。
さて、ここまでお話ししてきた「尺」ですが
スペースソリューション部の仕事ではよく遭遇します。
たとえば、木工やアクリルの板材を扱うときに
「サブロク」「シハチ」という言葉を使用します。
サブロク:3尺(W909㎜)×6尺(W1818㎜)
シハチ:4尺(W1212㎜)×8尺(W2424㎜)
このように、サイズを表した通称で
他にも「ニハチ(2尺×8尺)」や「サンパチ(3尺×8尺)」などがあります。
もちろん「脚立」も使用します。
====展示会場にて====
八幡 「すみません、ちょっと脚立貸してくださ~い!」
職人さん「いいよ~ 6尺で足りるかい?」
八幡 「大丈夫です!ありがとうございます!」
==================
という感じです。
仕事を始めたばかりの時は
「サブロク…?」「ロクシャク…?」となっていましたが、
意味を知ってしまえば、分かりやすいですね。
そういえば、「尺」について調べていた時に
ひな祭りのお内裏様や、やんごとなき雅なお子様がお持ちになっている
“シャク” についても知ることができました。
笏という漢字は本来音読みで「コツ」と読みます。しかし「コツ」という音は骸骨(ガイコツ)の骨の音と同じであるため、縁起が悪いと嫌われました。
そこで笏の長さが1尺(約30cm)あまりであったことから尺(シャク)の音を借り、笏を「シャク」と呼び習わすようになったのです。
らしいです。便利ですね、尺。
余談ですが、「一寸先は闇」ということわざがあります。
ほんの少し先の未来でさえ、どうなるか全く予測できないことを意味しますが、
「一寸=3.03㎝」なので、結構近いですね。
それでは、また。
次回はPS部 鹿ノ内さんです。
よろしくお願いいたします!
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+
ブログを見ていいね!したくなった方はこちら…
-ジオブレインfacebook-
http://www.facebook.com/GeoBrainCorporation
もっとジオブレインの仕事内容を知りたくなった方はこちら…
-ジオブレインHP-
https://www.geo-brain.com/
+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-:+:-+:-+:-+:-+:-+